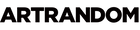PICASSO VU PAR BRASSAI
英語に「Recognition」という単語があるがその意味は「認識」や「見覚え」などといった感じになる。
要するにそれは見分けをつけるという人間の根源的な無意識的行動と言っても良いと思う。
白い紙に黒い点を二つ描くだけで人は無意識のうちにそれを目と認識してしまうという性質を持っているのである。
目は口ほどに物を言うとはよく言ったものだが二つの点を無意識に探してそれを「目」と認識するという人間の反応はもしかしたら弱肉強食の大昔に生き残るために本能的に養った能力なのか、または他を愛するために身につけた能力なのか、定かではない。
ピカソの友人であり自身も写真家でアーティストだったブラッサイが残したピカソを撮影した写真はピカソのかなり初期時代から続き社交場での写真やアトリエ風景に至るまで多岐に渡っている。
しかし中でも僕が注目するのはこの「目」を認識した作品についての記録として残された写真だ。
ブラッサイ自身も土壁に彫り刻まれた形に見出される「目」とそれによって人のように認識された形の写真を記録として多く残しているが彼はピカソの作品にも「目」を探して多く撮影している。
「目」といえばピカソ自身がまず人並外れた眼力の持ち主で彼自身の目も大きく鋭く光っていたが何よりもその彼の「目」の美に対する貪欲さは彼を近代芸術史における最高の芸術家として知らしめたのだ。
実際にブラッサイが撮影したピカソの初期から晩年に及ぶポートレイトでもピカソの「目」は常に鋭く大きく見開かれていてあの目に見つめられたら全てを見透かされてしまいそうだと怖くなるほど力強い。
ピカソはあの大きな「目」でその生涯で愛した数多くの女性達はもちろん、目の前の風景、静物、空間、時間までをも見つめ抜き美へと極めていったのだろう。
キュービズムの絵など見ているとこの「目」の存在を感じてしまうのだがものをあらゆる角度からひたすら見まくり、見抜き切った果てでなければあのようなものの見方はできるものではない。
ブラッサイはピカソがある日カフェで落ち込んでいた知人を慰めるために即興で作ったというカフェの紙ナプキンの作品も写真に収めている。
カフェにあった紙ナプキンを手に取ったピカソは形を切り抜き、そこに吸っていたゴロワーズのタバコの火を押し当てて二つの焦げ目をつけてみせた。
するとその紙ナプキンが可愛い白い子犬の顔になって現れたのだというがなるほど写真を見ると可愛い子犬に見えるから不思議だ。
いや、それは不思議ではないのかもしれない、ピカソにとっては対象物に二つの「目」を見出し「目」を与えて命を吹き込むことはキュビーズムからアヴィニョンの娘達まで描いた生涯を通して一貫して行ってきた芸術行為そのものなのだ。
ピカソにとって「目」を見出してそこから芸術を作り出すことは美を見出す才能であり善かれ悪しかれと言った相関関係など関係なく美の全てを徹底的に愛するための天才的な能力だったのかもしれない。